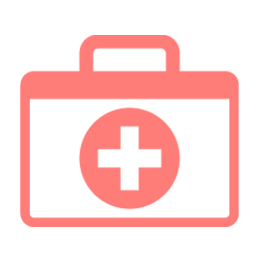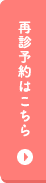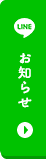【溶連菌感染症とは】
おもにA群溶血性連鎖球菌という細菌による感染症です。その他にもB群溶連菌によるものがありますが、ここではA群のみをお話しします。
【感染様式】
患者に直接接触することや唾液で感染します。
【症状】
A群溶血性連鎖球菌の一般的な感染症は、急性咽頭扁桃炎です。治療が行われないと中耳炎、副鼻腔炎、扁桃周囲膿瘍・咽後膿瘍(とても重症になることがあります)、化膿性リンパ節炎などがあります。しばしば、腹痛、嘔気、嘔吐などの消化器症状を伴うことがあります。
咽頭扁桃炎の症状としては咽頭痛、倦怠感、発熱、頭痛などです。鼻汁、咳、声枯れ、結膜炎は見られないことが多いです。3歳未満の子では典型的な症状が見られないことが多く、水溶性の鼻汁、微熱、不機嫌、食欲不振などが主な症状で(Streptococcal fever)、無症状のことも多いです。女児では外陰・膣炎を認めることもあります。
皮膚の症状としては丹毒、伝染性膿痂疹、猩紅熱、蜂窩織炎、壊死性筋膜炎などがあります。
丹毒は乳児や高齢者に多く、皮膚の表層ときに真皮に限局した感染症で、周囲の正常皮膚より盛り上がり、境界鮮明であることが多いです。
伝染性膿痂疹(とびひ)は、紅斑をともなう小水疱を形成します。やがて膿疱となり5日前後で厚いかさぶたになります。
猩紅熱は、紙やすり状の湿疹が全体(手掌、足底、口周囲には通常見られません(口囲蒼白))に見られます。
乳児では、外陰部や鼠蹊部に湿疹(ステロイド抵抗性)を認めることもあります。
蜂窩織炎は、急速に広がる皮膚および皮下組織の炎症性疾患で、局所の発赤、腫脹、自発痛、圧痛、全身の発熱を認めます。
壊死性筋膜炎は深部組織と筋膜の感染症です。急速に筋膜の壊死が拡大し、生命の危険が高い感染症です。一見しての診断は簡単ではありません。
怖い病気に「劇症型A群レンサ球菌感染症」があります。
初期症状は手足の腫れや激しい喉の痛みなどが出て、その後、急激に手足が壊死する症状を起こす場合もあります。
血圧低下や多臓器不全からショック状態におちいることもあり、発病後数十時間で死に至ることも少なくありません。致死率は、約30%になります。

【診断および検査および検査の適応】
咽頭培養がgold standardですが、咽頭炎、皮膚疾患には抗原による迅速検査が可能です。
3歳未満では通常検査の適応にはなりません。また症状のない方への検査も必要性はありません。ただし、リュウマチ熱や糸球体腎炎を発症した兄弟・家族内接触者は検査の必要があります。
Mclsaacによる溶連菌の咽頭炎の修正基準というものがあります。
- 発熱(38℃以上)1点
- 咳がない 1点
- 圧痛を伴う前頸部リンパ節腫脹 1点
- 白苔を伴う扁桃腺炎 1点
- 年齢:3〜14歳 +1点/15歳〜44歳 0点/45歳以上 ―1点
1点以下は検査なし、抗菌薬なし、対処療法のみ
2〜3点は溶連菌迅速検査陽性例のみ抗菌薬治療
4点以上は検査せず抗菌薬治療
となっています。
【治療】
ペニシリン系の抗生剤を10〜14日服用します。ペニシリンGが理想ですが、アモキシシリン(ワイドシリン、サワシリン、パセトシンなど)が使用されるのが一般的です。
日本では第三世代のセフェム系抗生剤の5日投与という方法をされている先生もいますが、まだ国際的には認められているものではないと思いますし、個人的な意見としては第三世代のセフェム系を安易に使用しない方が良いと思っています。この抗生剤にはまだリュウマチ熱を予防できるというエビデンスがないこと、また抗生剤に含まれるピボキシル基の副作用で低カルニチン血症があるためです。カルニチン欠乏症は、筋肉症状(筋肉痛、ミオパチー、筋肉壊死など)、低血糖、脂肪肝などの脂肪蓄積、脳症、高アンモニア血症(肝性脳症)、心筋症・心不全などを引き起こします。 重篤な欠乏症では不可逆的な脳・臓器障害を来すことが多く、低血糖による昏睡などで死に至ることもあります。
先ほども書きましたが、治療の目的はリュウマチ熱の予防です。
3歳以下の子どもはリュウマチ熱になることはまずありませんので、溶連菌を疑って咽頭の検査をしたり、抗生剤を投与することは原則必要ありません。
抗生剤を服用し解熱しており24時間経過していれば登園可能ですが、100%除菌できるわけではありません。10〜20%で菌が残っていることがあります。この場合は抗生剤に耐性であるのではなく、菌が細胞内に入り込んでいるため抗生剤の効果が低いのだと推定されています。細胞内移行率の高いマクロライド系を使用しますが、マクロライドに耐性の菌も多く報告されているため、効果が期待できないこともありえます。
【登校登園基準】
抗生剤を使用し解熱していれば、服用後24時間以上経過すれば登園、登校可能です。
【合併症】
代表的なものに急性糸球体腎炎(溶連菌感染後糸球体腎炎)とリュウマチ熱があります。
急性糸球体腎炎は溶連菌の治療により予防できませんが、リュウマチ熱は予防が可能です。溶連菌性咽頭炎の治療の目的はこのリュウマチ熱を予防することなのです。溶連菌では100以上のMタンパクというものが同定されており、特定の血清型(1、3、5、6、18、19、24型など)がリュウマチ熱の発症に関係があると言われています。49、55、57、59型などでは膿皮症と糸急性球体腎炎に関係しています。その他の血清型(1、6、12型など)は咽頭炎と糸球体腎炎に関係があると言われています。
治癒後に尿の検査をする先生もいますが、基本的には必要ありません。
腎炎になれば必ずと言っていいほど症状(頭痛、血尿、乏尿など)がでます。
2週くらいあとに体調が悪くなったり、おしっこが紅茶色やコーラ色になったとき(血尿)は受診が必要です。リュウマチ熱と異なり、抗生剤を服用しても発症率は下がりません。
そのほかに連鎖球菌感染性小児自己免疫神経精神障害:PANDAS(Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infection)というのがあります。溶連菌感染症との関連性が証明されたわけではありませんが、感染後に急性に発症する強迫性障害の症状やチックなどの症状を認めます。
もう一つは溶連菌感染後反応性関節炎:PSReA((post-streptococcal reactive arthritis)です。リュウマチ熱に似た関節の症状を呈しますが、後遺症は残らず治癒します。