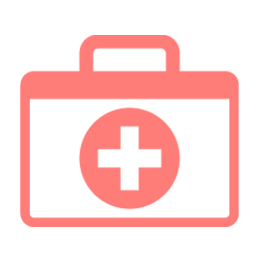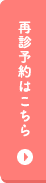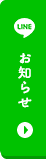皮脂欠乏症
保湿剤が必要な状態として、皮脂欠乏症があります。これは乾皮症、ドライスキンと同義語と考えて良いと思います。
しかし、皮脂欠乏症の明確な定義はありませんが、皮膚が乾燥して光沢を失い塑像になった状態を示すと思われます。
乾燥すると痒みを感じる神経繊維(C-fiber)が表皮内まで進展して痒みを感じやすくなります。掻くことにより皮膚バリア希望が破綻して悪化します(itch scratch-cycle)。
皮膚バリア
皮膚バリア機能を規定する因子として① 角質細胞間脂質、② 天然保湿因子、③ 皮脂の3因子が重要です。
皮膚は上から角層、顆粒層、有棘層に別れております。角質は保湿因子で満たされており、皮脂膜で覆われています。
- 角質細胞間脂質:セラミド(コレステロールから合成)
- 天然保湿因子:フィラグリンの分解産物(一部のアトイピー性皮膚炎ではこの遺伝子に異常があることが報告されています。)
- 皮脂:皮脂腺から分泌され皮膚表面の皮脂膜を形成して角層水分の蒸発を防いでいます。性ホルモンに影響されます。
皮脂欠乏症の原因
1.生理的要因
皮脂は性ホルモンの影響を受けるために、思春期前の小児は皮脂分泌量が少なく皮脂欠乏尿状態になりやすいです。
また、高齢者も汗腺や皮脂の機能が低下するため角質水分量が減少してしまいます。
2.非生理的要因
- 皮膚疾患に伴うもの
代表的なものはアトピー性皮膚炎、魚鱗癬、乾癬があります - 全身性疾患に伴うもの
糖尿病では発汗が減少することが知られています。慢性蕁麻疹で透析を受けていると角質水分量が減少しています。 - 医原性
抗がん剤、放射線治療などがあります。 - 外部環境の変化に伴うもの
エアコンの使いすぎにより相対湿度が低下し、過剰な洗浄によっても起こりえます。
保湿剤の種類
保湿剤には保湿を図るモイスチャライザーと、油性成分を配合してその皮膜を角質表面に作ることにより水分蒸発を抑えるエモリエントがあります。
つまり、エモリエントは皮脂膜の役目をし、モイスチャライザーはエモリエント効果に保湿作用が加わったものと考えられます。
- モイスチャライザー(moisturizer)
尿素、ヘパリン類似物質、セラミド、水溶性コラーゲン、ヒアルロン酸、アミノ酸など - エモリエント(emollient)
ワセリン、オリーブ油、ツバキ油、スクワランなど
角質柔軟化作用、バリア機能補強作用、水分保持作用とも優れているのはセラミドです。
ただ、医療用医薬品でセラミドを配合しているものはありません。
尿素含有製剤は角質妖怪作用があるため刺激性があり、バリア機能を低下することがあるので、特に小児への使用には注意が必要です。
ワセリンは角質軟化作用、保護作用に優れますが、べたつく、熱がこもることにより痒みが増すことがあります。
子どものスキンケアの方法
HP内の下記サイトを参考にしてください。
https://tsudashonika.com/childcare/skin-care/
保湿剤は全ての小児に必要であるわけではありません。
しかし、ハイリスクな乳児(アトピー性皮膚炎などの家族歴がある場合など)は、保湿剤を塗ることで食物アレルギーの発症を抑える可能性が高くなることが報告されています。
市販の保湿剤についての問題
市販の保湿剤に含まれる食物アレルゲンで、アレルギーになる可能性が示唆されています。「天然・オーガニック」を強調したマーケティング用語が記載されている製品は、穀物と精油を服も可能性が高く、より高価であることがわかっています。
また、「低刺激性」を強調したマーケティング用語が表示されている製品は果物や精油を含む可能性が低い傾向があります。
つまり、日本で販売されている「保湿剤」の多くに、食物成分や精油が含まれています。皮膚からの感作が言われていますので(経皮感作)、注意が必要です。
いままでにも石鹸で小麦アレルギーになったり、コチニールという色素が含まれた口紅でアレルギーになった事例が報告されています。