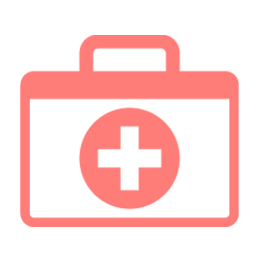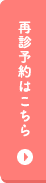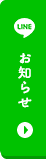【大腿骨頭すべり症とは】
大腿骨頭と大腿骨頸部のズレにより生じる股関節の疾患です。思春期の体重過多の男児に多く見られます。甲状腺機能低下症などの内分泌疾患に合併することもあります。
大腿骨頭の転位がなく体重を支えることができる安定型(慢性型)と、転移があり体重を支えることができない不安定型(急性型)があります。
【原因】
骨端線への過度の力学的負荷:肥満、過度のスポーツ活動
骨端線の脆弱性:成長ホルモンの分泌亢進、性ホルモンの分泌低下、くる病、過去の放射線治療など
上記二つの原因が考えられています。
肥満と密接な関係がある疾患と認識されていましたが、最近では過度のスポーツ活動が原因となったケースが増えています。
【頻度・性差・好発年齢】
発生率は好発年齢層の人口10万人あたり男性で2.22人、女性で0.76と推定されています。
発症年齢は思春期例がほとんどですが、まれに幼児例や20歳を越すれいがあり、この場合は内分泌疾患を伴うことを疑います。
約半数に一見して肥満があるのも特徴です。
【症状】
痛みのため逃避性跛行とTrendelenburg歩行が特徴です。逃避性跛行とは痛みのため足が接地する時間が短くなるような歩き方のことを言います。
しかし、痛みを訴える場所は必ずしも股関節であるとは限りません。
患児は外旋して歩くため、足部や下腿にストレスがかかり、膝や下腿遠位部に痛みを訴えることも多いです。
そのため、確定診断が遅くなるケースも少なくありません。Trendelenburg歩行は歩くときに骨盤が揺れる歩行する歩き方のことです。
【診断】
上記の臨床症状と整形外科にて股関節の単純レントゲン写真の前後像および側面像により診断されます。
約30〜60%と両側性の頻度も高いのでレントゲンは両股関節を撮影する必要があります。
レントゲンでは、アイスクリームがコーンから滑り落ちるように見られ、大腿骨頭から軸がずれていることを示しています。
早期の場合にはMRIが有効のこともあります。
【鑑別診断】
逃避生歩行やTrendelenburg歩行を呈する鑑別としては発育性股関節形成不全(先天性股関節脱臼)とペルテス病(レッグ・カルベ・ペルテス病; LCPD)があります。
一般には股関節脱臼は発症が早く2歳頃に発症します。
短縮した足の長さを補うために患側が爪先歩行を取ることが違いです。
ペルテス病は通常4〜8歳の小児に発症します。
単純性股関節炎も鑑別の対象となり、典型的には3〜10歳くらいの男児に上気道炎の数日後に股関節の痛みと膝などに広がる痛みが見られます。
【治療】
治療の目的はすべり症の進行を防ぎ、骨壊死、軟骨融解、および大腿骨臼蓋インピジメント(骨や筋肉との衝突が生じることによって、組織の損傷が起こって痛みが生じる状態)の合併症を回避することです。
股関節に体重がかからないように松葉杖、車椅子、ストレッチャーなどを使用します。
大腿骨頭の外科的固定術を行います。
体重の減量は血管障害とそれに続く大腿骨頭の阻血性壊死のリスクを高めるため行いません。
【合併症】
大腿骨頭壊死、軟骨融解、変形性股関節症などが挙げられます。
【最後に】
大腿骨の頭の部分が滑ってしまう重大な病気です。きちんと治療しないと歩くのに不自由する状態になる可能性もあります。手術治療と長期間の運動制限が必要です。多くの場合、肥満や過剰なスポーツ活動が原因なので、これまでに生活スタイルに問題がなかったか見直して見ましょう。