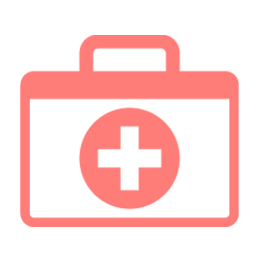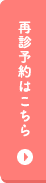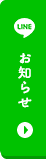プラネタリウム(Planetarium)という言葉は惑星を意味する「プラネット(Planet)」と「見る場所を意味するアリウム(arium)」を組み合わせた造語です。水族館は英語で「水を見る場所、アクアリウム(Aquarium)」と言いますよね。初めてのプラネタリウムは1781年オランダのアマチュア天文者であるアイゼ・アイジンガーが自宅に作った太陽の周囲を回る水星、金星、地球、火星、木星、土星だけを眺めるものでした。名前の通り惑星を見るもの、プラネタリウム(Planetarium)でした。現在のような星空を見るプラネタリウムが初めて作られたのは1923年、ドイツのミュンヘンにあるドイツ博物館から依頼を受けたカール・ツァイス社が発明したものです。光学機械、特にレンズなどで有名な会社ですよね。「カール・ツァイス1号」と呼ばれていますが、その本体には「プトレマイオス式プラネタリウム」の表記があります。プラネタリウムは天球が動くため天動説を唱えたプトレマイオスに敬意を表しているのでしょう。そうです2023年はプラネタリウムが発明されてちょうど100年でした。それから2年間各地で祝100年のイベントが行われています。日本では1937年3月13日、大阪市立電気化学館に「カール・ツァイスII号」が設置されたのが最初です。日本では当初「天象儀(てんしょうぎ)」と訳されました。2037年にも何かお祝いイベントがあるかもしれません。是非参加したいものです。もう少しプラネタリウムに関してはお話ししたいので期待してください。
-
予防接種予約 ・お問合せ
Tel.03-5477-7736