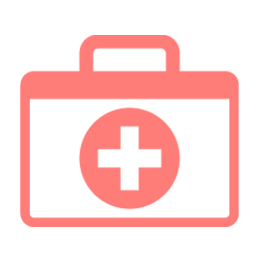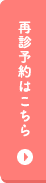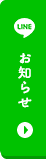古代の人は星をよく見ていました。そして、星は同じように動くことを知っていました。その中で軌道が定まらない星があることに気がつきました。それが惑星です。英語ではPlanetと言います。古代ギリシャ語で「さまようもの」とか放浪者という意味です。この「さまよう」という意味を日本語では「惑う」と解釈したのです。だから惑星と呼ぶのです。太陽から近い順に水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星と8つの惑星が太陽にはありますが、太陽に近いほど公転が速いのです。その速度の差により地球から見える軌道がさまようのです。
準惑星は、惑星の定義を満たさないものの、ある程度の質量を持ち、ほぼ球形をしている天体です。冥王星は、2006年に惑星の定義から外れ、準惑星に分類されました。それは以前にも話しましたよね。
太陽の周りを公転する天体のうち、惑星と準惑星およびそれらの衛星を除いた小天体を太陽系小天体と呼び、それらのうちおもに木星の軌道周辺より内側にあるものを小惑星と呼びます。
恒星は英語でFixed Starsであり、夜空での相対位置が変わらないことからFixed Stars、日本語では恒星と呼ばれています。ちなみに、衛星の英語名は Satellitesです。Satelliteはラテン語の「従者」という意味なので惑星に従っているということですね。ちなみに「衛」は衛兵からもわかるように、「周囲にいて守る」という意味です。
「古代エジプトの話しよう」で検索してみてください。つだ小児科クリニックがトップに出てくるかもしれません。